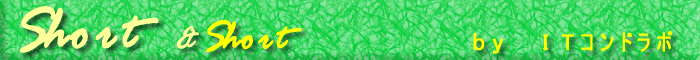 | |
|
制約条件理論(TOC)可能性のあるフィロソフィーなれど 期待どおりのポテンシャリティと | |
|
4月26日、日本総合研究所の制約条件理論(TOC:theory of Constraints)のチュートリアルレベルのセミナーに参加した。実践的なTOCの普及を狙った洗練された内容であった。成功事例が出始めたフェーズと理解している。ただ、当然のことながら生産システムなどの組織全体に拘る問題であるため、今までも壁として展開を阻んだ経営陣のリーダシップ、全体最適発想、組織風土・企業文化の変革などを不可欠とする。私の場合、TOCとの出会いは、2001年秋であった。ベストセラーとなった「theGoal(DR.EliGoldratt)」によって大いに耳にするようになったのではと思う。 概要として、一見複雑に見える問題対しシンプルな解決策をシステマティックに提供する、マネジメントフィロソフィーである。組織全体の業績を改善するためのプロセスとして、 | |
|
|
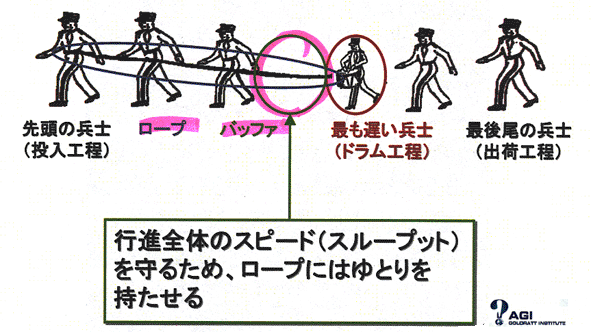 |
|
①制約条件を特定する。 | |
|
具体例で示すと上記の行進中の兵士隊列がある。隊列が長いということは、仕掛りが多くなり、スループットの低下を招く。どうすれば行進全体のスピード(スループット)を落とさずに隊列が長くなることを防げるだろうか。まず、ボトルネックとなっている最も遅い兵士が行進のスピードを決定しているとし(ドラム工程という)、次に隊列の広がりを防ぐために、最も遅い兵士と先頭兵士をロープで結ぶ。このロープは行進全体のスピードを守るため、ロープにゆとり(DBR:ドラムバッファーロープ)を持たせる。というもの。JITが兵士の足をすべてロープで結ぶという方式に対し軽微なマネジメントシステムと言える。これからも言えるように、全体スループットを適格に向上できる有効な手法と言えるのではないだろうか。 | |
| |
|目次へ|